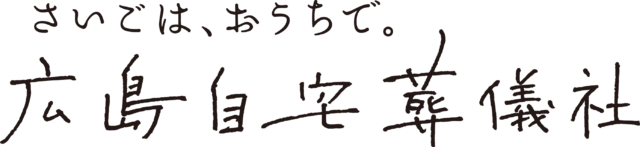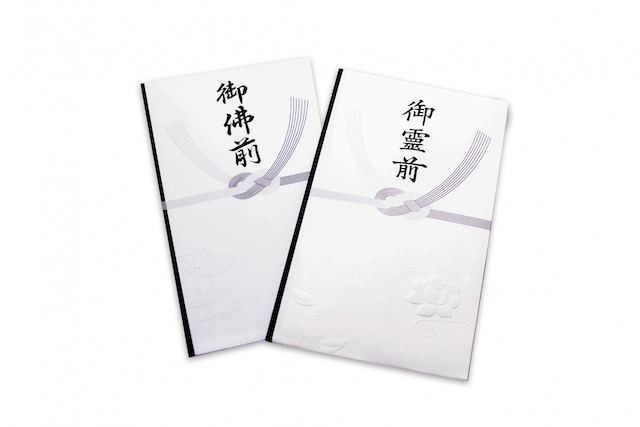死産をされた赤ちゃん(胎児)の葬儀、火葬はどうなる?わかりやすく解説
更新:2025.03.10
妊娠12週以降に流産や死産となったら、火葬をする必要があります。
悲しみの中、手続きを進めるのはとても辛いものです。
多くの人は葬儀社の手を借り、赤ちゃんを見送ります。
「死産した赤ちゃんのために、しっかり葬儀を行うべき?」
「なるべくゆっくり見送りをしたい」といった疑問や希望をお持ちの方のために、死産となってから火葬に至るまでのプロセスをご案内します。
目次
妊娠12週以降の流産、死産は火葬の必要がある
お腹の中で亡くなった赤ちゃんでも、火葬が必要な場合があります。
妊娠12週以降の流産、死産は、死産届を出し、火葬を行わなければなりません。
また、妊娠24週以降の死産であった場合は、24時間を過ぎてから火葬をしなければなりません。
死産届は死産があってから7日以内に、病院の所在地か両親の所在地である市区町村役所に提出します。
死産届を提出すると「火葬埋葬許可証」が発行され、火葬ができるようになります。
死産後、病院で行われること
死産となった後、すぐに火葬の手続きを行う必要はありません。
無事に生まれてくることを願っていた命を突然亡くした両親の多くは、気持ちの整理がつかないことでしょう。
赤ちゃんの状態にもよりますが、死産であっても通常の出産と変わらない、あるいは思い出に残るような工夫をしてくれる病院があります。
赤ちゃんを抱っこしたり、添い寝したり、一緒に写真を撮ったり、へその緒や髪の毛、爪を保管してくれたり……。
とくにへその緒や髪の毛、爪の保管は、供養に役立つことがあります。
後にも述べますが、死産であった赤ちゃんの遺骨を残して火葬するのは難しいためです。
手形や足形も、取れる状態であれば取っておくのがおすすめです。
お母さんの体調が少し戻ったら、赤ちゃんが確かにお腹の中にいてくれたことを実感できるような何らかのケアをしてもらえないか、病院のスタッフに頼んでみましょう。
死産となった赤ちゃんの見送り方は3つのパターンがある
死産となった赤ちゃんの見送り方には、以下の3つのパターンがあります。
葬儀社に必要なもの一式を依頼し、葬儀はせずに火葬のみを行う
最も多いのがこのパターンです。
棺や骨壺など必要なものを葬儀社に依頼し、葬儀社のアドバイスを受けながら火葬のみを行います。
費用相場はおおよそ5万円〜8万円程度です。
葬儀社に依頼して、火葬だけでなく葬儀も行う
「この世に生を受けられなかった赤ちゃんであっても、しっかり見送りたい」と希望する場合は、葬儀を行うこともあります。
葬儀社に相談して式場を手配してもらい、身内を中心とした小さな葬儀を行います。
胎児の葬儀自体が珍しいので費用相場はありませんが、20~30万円程度とみておけばよいでしょう。
僧侶に読経を依頼する場合は別途お布施が必要です。
葬儀社に依頼せず、家族が必要なものを手配して見送りをする
死産した赤ちゃんの見送りに最低限必要なのは、「棺」「火葬場の手配」「火葬場まで赤ちゃんを運ぶ車」です。
これらは家族が手配することも可能です。
インターネット通販などで赤ちゃん用の棺を買い、お父さんやお母さんが火葬場に予約連絡を入れ、火葬場までは家族が車を運転します。
病院によっては棺を用意してくれるところもありますので、相談してみると良いでしょう。
費用は、利用する火葬場の料金にもよりますが、全部で3~5万円程度に収まることが多いでしょう。
死産届を受け取ってから火葬するまでの流れ

火葬のみを行うときも、葬儀と火葬を行うときも、全体の流れはおおよそ同じです。
死産となってから火葬するまで、一連の流れをご案内します。
家族で今後のスケジュールを話し合う
お母さんの体調が少し落ち着いたところで、家族みんなで以下について話し合いましょう。
*火葬のみとするか、葬儀も行いたいか
*火葬はどのタイミングが良いか
*棺や骨壺などの必要品は葬儀社に依頼するか、それとも自分たちで手配するか
話し合いの結果を、依頼する葬儀社へ伝えます。
死産証書を受け取る
死産となった後、医師から死産証書(死胎検案書)が渡されます。
死産証書の左側が死産届になっており、死産があってから7日目までに市区町村の役所へお父さん(またはお母さん)が届け出ます。
葬儀社が代行することも可能です。
赤ちゃんの安置
死産した赤ちゃんは、お母さんの退院まで病院に安置されます。
お母さんが退院したら、自宅へ連れて帰る場合と、葬儀社の安置室などで安置する場合があります。
自宅安置の場合は、葬儀社に火葬までの接し方を相談しましょう。
場合によってはドライアイスが必要になることもあります。
必要なものを手配する
葬儀社と葬儀や火葬の日程を打ち合わせ、火葬場の予約や棺の手配を行ってもらいましょう。
必要品を自分で手配する場合は、棺を手に入れます。
胎児用の棺は、病院で支給してくれるところもありますが、それができない場合は、インターネット通販などで販売されており、紙製の箱や段ボールで自作することも可能です。
通販で手に入れる場合は、火葬日程に間に合うよう注意します。
また、火葬場へ予約を入れます。
赤ちゃんの火葬では、遺骨が残らない場合も少なからずあります。
もし赤ちゃんの遺骨を残したい場合には、予約時に火葬場へ相談しましょう。
朝一番の火葬はまだ炉が熱くなっていないため、遺骨が残る可能性が高くなります。
葬儀
火葬の前に葬儀を行いたい場合は、火葬予約時間の2~3時間前に葬儀を行います。
火葬の前日までに葬儀を済ませることもあります。
葬儀の形式は、お別れの手紙を読むなどを中心とした無宗教葬や、僧侶が読経する昔ながらの仏式葬儀など、家族の希望に沿って行えます。
ただし、いつもお世話になっているお寺が胎児の葬儀も行ってくれるかどうかは、相談してみないと分かりません。
多くのお寺は、お引き受けくださるはずです。
火葬
火葬予約時間に間に合うよう、火葬場に向かって出発します。
これを「出棺」といいます。
出棺前には、棺を開けて最後のお別れをするのがおすすめです。
ただし、家族の体調や気持ち、赤ちゃんの状態によっては、棺を開けずにお別れをすることもあります。
お別れの時間では、赤ちゃんの体のまわりにお花を入れてあげます。
また、赤ちゃんのために準備していた帽子、靴下、布製おもちゃなど、少量の燃えるものであれば棺に入れることが可能です。
火葬後、遺骨を骨壺に納めます。
もし遺骨が形としては残っていなくても、遺灰を納められる場合があります。
会食
火葬後、一般的な葬儀のように参列者が集まって会食をとることもあります。
会食を行うかどうかは、家族の判断で構いません。
会食を行う場合は、会場を事前に予約しておくとスムーズです。
葬儀式場で葬儀を行う場合は、式場内の会食会場を使うことができます。
死産した赤ちゃんの葬儀、火葬を行うときの服装
一般的な葬儀の場合は喪服を着用しますが、死産した赤ちゃんの葬儀、火葬では、平服でもよいとされています。
平服とは、喪服ではないけれどカジュアルすぎない、改まった服装です。
男性の場合
黒や紺、グレーなど落ち着いた色味のスーツを着用し、ネクタイやベルト、靴下、靴といった小物も落ち着いた色にします。
ワイシャツは白です。
服も小物も、光沢のある素材を避けましょう。
女性の場合
黒や紺、グレーなど落ち着いた色味のワンピースに、同系色のジャケットやカーディガンを羽織ります。
ストッキングの色は黒がよいとされていますが、ベージュでも構いません。
落ち着いた色味のスーツも着用できますが、とくにお母さんはお腹にゆとりを持たせた服装にしましょう。
靴やバッグなどの小物も、落ち着いた色味のものにします。
化粧はラメなど光沢の入っていないメイク用品を使い、薄目に仕上げましょう。
髪は後ろで一つに束ねます。
なお、家族の話し合いにより喪服で参列することも可能です。
平服であれ、喪服であれ、方針が決まったら参列者全員に共有しましょう。
家族みんなが納得できる葬儀が何より大事
この世に生を受けることがなかった赤ちゃんの見送りは、家族が本当に納得する形でできたかどうかによって、その後の気持ちが違ってきます。
「かわいそうで、姿を見るのも辛い。早く火葬をしたい」と考える人もいれば、「生まれてこなくても、家族は家族。しっかり見送りたい」と思う人もいるでしょう。
もしかしたら、赤ちゃんに対する気持ちは家族の中でも違うかもしれません。
とくに、お腹の中で命を育んできたお母さんの想いは尊重する必要があります。
いろんな考え方や選択肢があることを念頭に置いてよく話し合い、最も納得できる形でお別れをしましょう。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。