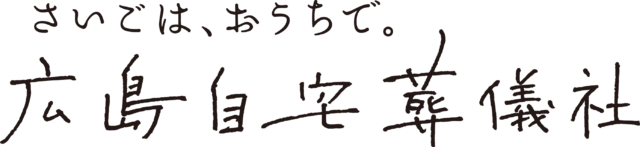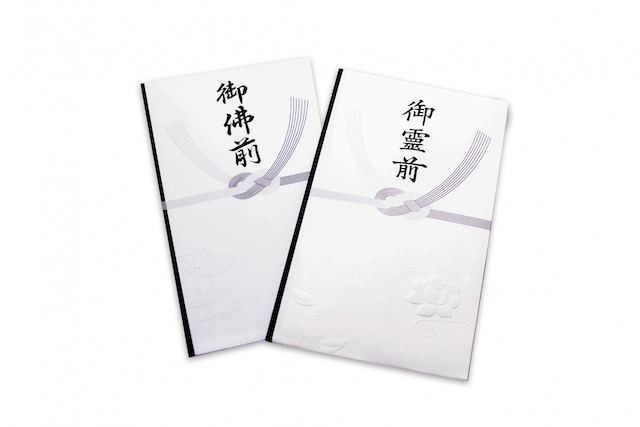死産と流産の違いは?何週から火葬が義務付けられる?わかりやすく解説
更新:2025.03.10
赤ちゃんをお腹で育んでいる最中に亡くしてしまうのは、お母さんにとって、とても辛いことです。
日本では、お腹の中で赤ちゃんがある程度大きくなってから亡くなると、火葬をしなければなりません。
その境目は妊娠12週であり、12週以降であれば火葬が義務づけられています。
「流産と死産の違いって何?」
「どんなふうに赤ちゃんを亡くすと火葬が必要になるの?」と疑問に思っている方のために、死産と流産の違いや、火葬はいつから義務づけられているのかについて解説します。
目次
流産とはどのような状態か
まずは流産について具体的に説明しましょう。
「流産」といって多くの人が思い浮かべるのは、妊婦がある日突然激しい腹痛に襲われ、その後子宮から大量の出血があるという状態でしょう。
このような流産は「進行流産」と呼ばれ、自覚症状があり、子宮の内容物の多くは自然に排出されます。
進行流産に対して、出血や腹痛といった自覚症状がないのに流産してしまう状態を「稽留流産」といいます。
産科へ検診などに行き、超音波検査を行うことで初めて赤ちゃんが亡くなっていることが分かります。
稽留流産になると、いずれ生理のような痛みとともに子宮内の組織が排出されるケースが多いですが、手術によって子宮の中をきれいにすることもあります。
死産とはどのような状態か
死産には2つの状態があります。
1つは、妊娠中に母体の中で赤ちゃんが死亡してしまっている状態です。
妊娠中の女性が、下腹部痛や不正出血など違和感に気づいて産科へ駆け込み判明する場合もあれば、定期健診で「赤ちゃんの心臓が止まっている」と医師から告げられることもあります。
2つめは、分娩中に死亡してしまう状態です。
へその緒が赤ちゃんに絡まってしまう、胎盤に異常があるなど様々な要因で、それまで健康とみなされていた赤ちゃんであっても、亡くなってしまうことがあります。
もし生まれてすぐに赤ちゃんが亡くなってしまったとしても、母体の外で赤ちゃんが生きていた時間があったとしたら、死産には含まれず新生児死亡として扱われます。
死産と流産の違いは週数にある
死産も流産も、赤ちゃんが生存した状態で生まれなかったという点では同じです。
死産と流産の違いは、週数にあります。
日本においては、医学的には妊娠22週以降に赤ちゃんがお腹の中などで亡くなることを「死産」、22週未満であれば「流産」と定義しています。
なぜ妊娠22週が分かれ目になるのかといえば、22週以降に生まれた赤ちゃんは、母胎の外で生存できる可能性があるためです。
妊娠22週から36週6日までの出産は「早産」と呼ばれ、生存した状態で母胎から排出された場合、医療的サポートを受けることができます。
つまり日本の医療では、22週以前は「お腹の中でなければ生きられない命」、22週以降は「お腹の外でも生きることができるかもしれない命」に分けられているといえます。
よって倫理的な観点から、妊娠22週以降の人工妊娠中絶は禁止されています。
火葬が義務づけられるのは妊娠12週以降
日本の医学においては妊娠22週以降に胎児が亡くなることを死産としていますが、法律ではその期間が違います。
「昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)」では、死産を「妊娠第四月以後における死児の出産」、つまり妊娠12週以降としています。
医学的な定義と、10週の差があります。
法律では、全ての死産は届け出なければならず、また「死体」として火葬または埋葬を行わなければなりません。
日本では、埋葬ができるお墓が非常に少ないため、一般的には火葬が行われます。
医学的定義と法律的定義が違うので紛らわしいですが、「妊娠12週以降に流産、死産した場合には火葬が必要」と考えましょう。
人工妊娠中絶であっても12週以降は火葬が必要
死産、流産の他に、人工妊娠中絶で赤ちゃんが亡くなることがあります。
人工妊娠中絶は人為的に妊娠を終了させることです。
母体保護法に則り、手術を行う場合と薬を服用する場合があります。
人工妊娠中絶の場合も、妊娠12週以降に行われたのであれば届出と火葬が必要です。
死産届の出し方と火葬までの流れ
死産後の届出と火葬手続きの内容や流れを、分かりやすく説明します。
手順1
医師あるいは助産師から、「死産証書」または「死胎検案書」を受け取ります。
「死産証書」は、医師が死産に立ち会う場合に発行されます。
「死胎検案書」は、医師が死産に立ち会わない場合に発行されます。
手順2
死産証書(死胎検案書)の左側は「死産届」になっているため、死産届に父母の名前や本籍などの必要事項を書き入れます。
手順3
死産届を、死産があった病院の所在地か、届出人となる両親の所在地の市区町村役所に提出します。
提出期間は、死産があった日から7日以内です。
死産届の提出は、未婚の場合などやむを得ない事情がない限りはお父さん側が行います。
実際、死産してからしばらくは女性の身体的負担が大きいため、お父さんが手続きを行うのが一般的です。
赤ちゃんの葬儀を葬儀社へ依頼した場合、葬儀社が代行してくれます。
手順4
役所窓口に死産届を提出すると、火葬埋葬許可証が発行されます。
この後、火葬の予約を行います。
両親が自ら火葬場へ連絡して火葬の予約を取ることもできますが、葬儀社へ依頼することも可能です。
手順5
棺を用意します。
胎児用の棺はインターネット通販などで手に入りますし、葬儀社に棺だけを依頼する人もいます。
病院によっては、一般的な棺ではありませんが、代用できる専用の容器を用意してくださるところもありますので、確認をしてみると良いでしょう。
心を込めて、段ボールや家にある紙箱などで手作りする人も見られます。
手順6
予約時間までに火葬場へ出向き、火葬を行います。
死産となった赤ちゃんを自家用車で運んでも、法律違反ではありません。
葬儀社に車を手配してもらう人もいます。
死産後、両親だけで火葬までの手続きを済ませるケースもあれば、葬儀社に依頼して葬儀を行うケースもあります。
死産となってから赤ちゃんの葬儀、火葬に至るまでの詳細なプロセスは、別記事「死産をされた赤ちゃん(胎児)の葬儀、火葬はどうなる?わかりやすく解説」に書きますので、参考にしてください。
妊娠24週以降の死産は、死産後24時間を経過するまで火葬できない
法律では、妊娠24週以降に死産となった場合には、死産後24時間を経過するまで火葬ができません。
「死後24時間が経たないと火葬できない」という決まりは、胎児でなくても同じです。
火葬の予約をする場合は気をつけましょう。
なお、死産から火葬まで期間を長く取る場合には、腐敗が進まないようドライアイス等で赤ちゃんの体を冷やす必要があることもあり得ます。
葬儀社に依頼すれば、赤ちゃんの体に合った分量のドライアイスを手配してくれます。
火葬の日程は家族みんなが納得できるタイミングに
妊娠12週以降の流産、死産では役所への届出と火葬が必要になります。
死産を経験したお母さんが入院するなかで、お父さんや他の家族が協力し合って手続きをするということです。
実際に手続きをする家族は、悲しむ間もなく忙しいと感じるかもしれません。
しかし、赤ちゃんを失ったお母さんは、体はもちろんのこと、心も深く傷ついています。
まわりの人は、いたわりが必要な状態が長く続くと考え、お母さんが孤独感を募らせることのないよう配慮しましょう。
とくに火葬の日程を決めるときには、まだ入院中であるお母さんの意向を尊重するのが大事です。
「せめて自分が退院してから見送りたい」「我が子と一秒でも一緒にいてあげたい」と願う人は多く、2週間先の火葬予約を希望した例もあります。
そのような場合は、赤ちゃんの状態を少しでも良好に保てるよう、葬儀社に相談しましょう。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。